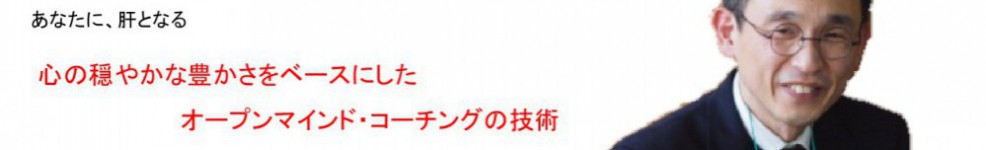「意識は、共同性は排他性へと変質する。」
公開日:
:
最終更新日:2017/02/22
et cetera
> そこに所属しているという意識から、そこを自分が所有しているという意識に変わったとき、共同性は排他性へと変質する。
> 星野智幸
(折々のことば 選・鷲田清一)
「共同性から排他性へ」という話はわかる。
でも、むずかしい話。
「所属」には、
「偶然席に座らせてもらった」から、
「いつ居てもいい」
「自分の定位置がある」
「主宰者と仲が良い」
「運営の一端を担っている」
「自分が居ないと動かない」
「運営を決定し、実際に運営する一人である」
までなだらかに変わる。
いつまでも「お客様」の意識でいては仕方ないし、
「運営するメンバー」の自覚がないと、責任は引き受けられないし、所属している意味はない。
個人も、組織も、時とともに変わるものだから
個人の暴走を止めるのには十分注意がいる。
(主宰者が決めなければ、だれがどのように判断するか、誰にもわからない)
だとすると、
「共同性から排他性へ」
は、人間の生理として仕方ないことだろうか?
多様性を高めていくことは組織に絶対必要なことと言っていい。
だから、
組織が続き、人が増える際に、
組織の目標と手段は、メンバー間でことばの誤解をなくしつつ共有することが、解決策となるだろうか?
関連記事
-

-
社会で生きるための「コミュニケーション力」は「コーチングの心」がベースになる
姉妹Blogサイトの記事 http://views.core-infinity.jp/2016/12
-

-
あなたは『自分の意思を信頼して』いますか?
コーチングの場でも、こういう人がいます。 いやいや「覚せい剤依存症患者」ではなくて、 『意思
-
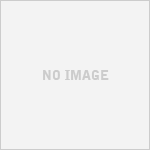
-
新聞記事「100万人のうつ」
最近、朝日新聞夕刊1面に新しい特集コラムが連載され、興味深く読んでいます。 『人脈記 100
-
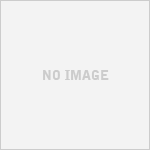
-
「体験する時間」が文章になるまで
体験する時間 身体で受け止める時間 エッセンスに気づくまでの時間 文章にする時間 メール通信、Ame
-

-
僕には「ストレス」は少ないけれど「課題」はいっぱいある。
9/25 組織活性化コーチング「コーチングでストレスマネジメント1入門編」http://jca-ky
-

-
『コーチをコーチングしてコーチング力をアップするトレーニング』
『コーチをコーチングしてコーチング力をアップするトレーニング』 コーチングを学ぶために
-

-
「承認」の仕方を、ロボット教室に学ぶ
ロボット教室でのある生徒との会話。 かなり作るのに苦労するロボットを前にして。 もう少
-

-
「ほめる」と「叱る」をするときの盲点
「ほめる」と「叱る」について、ある人の記事で気づいたことがありました。 部下をきちんとほめた