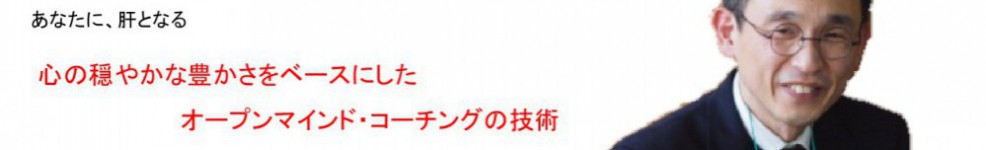「意識は、共同性は排他性へと変質する。」
公開日:
:
最終更新日:2017/02/22
et cetera
> そこに所属しているという意識から、そこを自分が所有しているという意識に変わったとき、共同性は排他性へと変質する。
> 星野智幸
(折々のことば 選・鷲田清一)
「共同性から排他性へ」という話はわかる。
でも、むずかしい話。
「所属」には、
「偶然席に座らせてもらった」から、
「いつ居てもいい」
「自分の定位置がある」
「主宰者と仲が良い」
「運営の一端を担っている」
「自分が居ないと動かない」
「運営を決定し、実際に運営する一人である」
までなだらかに変わる。
いつまでも「お客様」の意識でいては仕方ないし、
「運営するメンバー」の自覚がないと、責任は引き受けられないし、所属している意味はない。
個人も、組織も、時とともに変わるものだから
個人の暴走を止めるのには十分注意がいる。
(主宰者が決めなければ、だれがどのように判断するか、誰にもわからない)
だとすると、
「共同性から排他性へ」
は、人間の生理として仕方ないことだろうか?
多様性を高めていくことは組織に絶対必要なことと言っていい。
だから、
組織が続き、人が増える際に、
組織の目標と手段は、メンバー間でことばの誤解をなくしつつ共有することが、解決策となるだろうか?
関連記事
-
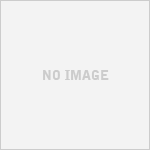
-
最近開いている3冊の本
最近、平行して読んでいる本、3冊を紹介します。 TA TODAY―最新・交流分析入門
-

-
「ほめる」と「叱る」をするときの盲点
「ほめる」と「叱る」について、ある人の記事で気づいたことがありました。 部下をきちんとほめた
-

-
「ストレートに意見を言う」 「人の心に土足で入らない」
> ストレートに意見を言ってきますが、人の心に土足で入るようなことはしない。スリッパを履いて入ってく
-

-
チームワークはどこにある? その6
Group Weight Lifting and Tug-of-War Event / prash
-

-
格付けと、空中浮遊、千里眼、壁抜けの能力
格付けの前提になるのは規格化です。「ほかの条件をすべて同じにする」ことなしに客観的な格付けはでき
-

-
「私のヤル気を上げる言葉」を口に出してみる
京都チャプター7月例会「部下のヤル気を上げるコーチング」の講師をしてきました。 公式の報告
-

-
「内からのメッセージ」と「自分ってどんな人?」
最近、このようなメッセージをお伝えしています。 ふと気づいたこと、意識で思考して出てきたの
-

-
目標と承認はかなり近い関係
多くを所有して重装備になって、 いろいろできるようになって、 お金とか人間関係とか人に恥じ
-

-
「何かをしてあげる」のではなく、「一緒に歩む」
「あなたが『何かをしてあげる』必要はない。大切なのは『人々と一緒に歩む』こと」 (特派員メモ ルブ
-

-
うまくいくパターンの選択肢を増やすために
前者・後者論の向江さんの以下の記事 「後者に学習能力はない」 昨日の僕の記事