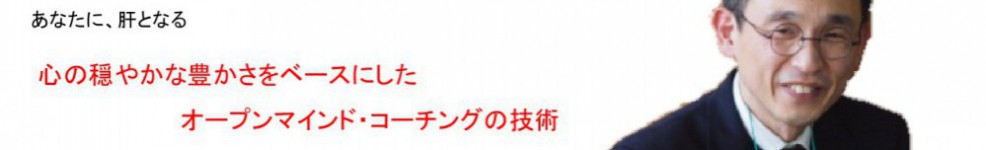うまくいくパターンの選択肢を増やすために
公開日:
:
et cetera
前者・後者論の向江さんの以下の記事
「後者に学習能力はない」
昨日の僕の記事
コーチを雇う理由、もしくはコーチの役目
https://pro.core-infinity.jp/2016/08/sycophant/
は、繋がっているように思います。
為末さんの高野コーチからの無茶なトレーニングメニューの話は、
~~~~~~~
「これくらいの確信度でも、人の言うことを聞いてとりあえずやってみることで、
思ってもみなかった上手い行き方や、結果になったり、
世界が広がることがあるんだな」
ということ自体が、パターンとして学習されます。
(向江さんのリンク先より引用)
~~~~~~~
のトレーニングをしていたことになるのでしょう。
この時の課題。
「後者はこだわりが強い(人から指示されるのが得意ではない)」
これがあるからこそ、
『信頼しているトレーナー・コーチ』
が必要なんですね。
ほとんど、「鶏が先か、卵が先か」になりますが、
『信頼される』
って大切です。
関連記事
-

-
主体性をとるか、体罰をとるか
> キーワードは「生徒が自ら考えて行動する」。 > 幹となる部の約束事は、「リスペクト(尊敬する)
-

-
チームのメンバーが違うことを前提にやることが、チーム力を発揮すること
> 利用者のみなさんと一緒にぼーっとしているときがあって、そういう何もない時間が怖くないというか。
-

-
ノーサイン野球を目指しますか?
山口)高川学園、「ノーサイン野球」掲げて挑んだ夏 - 高校野球:朝日新聞デジタルhttp://www
-

-
「すぐには教えない,でも詳しく教える」
リンク先は、高校数学の塾の先生の記事です。 タイトルだけでここの話は十分です。 「すぐには教
-

-
勤務日自由、好きな作業だけでよいという会社
ある工場の取り組みがあります。 [武藤北斗からの返答] togetter「好きな日に連絡なしで
-

-
チームワークはどこにある? その4
Group Weight Lifting and Tug-of-War Event / prash
-

-
「主体性」についてあれや、これや
日本コーチ協会 京都チャプター 7周年記念セミナー 日 時:11月27日(日) 10:00~
-
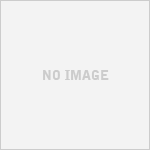
-
「メールの書き方を新入社員に教える」
「メールの書き方を新入社員に教える」 その指導のコツは、ほかの場面でも応用できそうです。
-
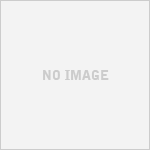
-
企業支援セミナー「報連相~指示待ち型から提案型~」(企業年金研究会)の参考サイト
以下は、2012年1月19日企業支援セミナー「報連相~指示待ち型から提案型~」(企業年金研究会)の
PREV :
コーチを雇う理由、もしくはコーチの役目
NEXT :
「部下との向き合い方」ではなく、「自分の心との向き合い方」