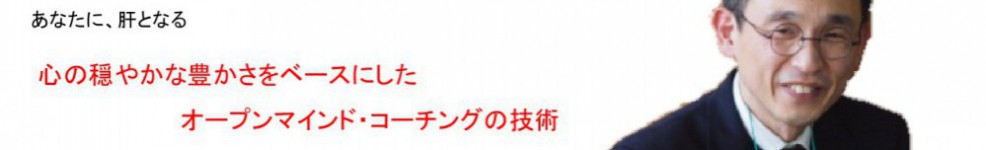主体性をとるか、体罰をとるか
公開日:
:
最終更新日:2016/12/24
et cetera
引用した記事は、表題通り「部活の体罰なくせるか」というテーマの文章から。
『主体性』
という意味では、まったく同じです。
コーチークライアント
上司ー部下
親ー子供
先生ー生徒・学生
それでも「体罰が場合によっては必要だ」という意見が出てくるのは、
左側の人たちが「手を抜いているから」としか言いようがない。
手を抜いていないのだったら、
「経験していない」・・・「だからその結果を知らない。実感がない。確信がない」
「生徒の主体性に任せる方法を知らない」
「生徒の主体性に任せるときの自分のふるまい方、観察ポイントを知らない」
「今やっているこの方法で正しいか確信がない」
でしかない。
そして、
「自分と違う方法だと不安になる」
「成果が出ないと不安になる」
「表向きの目標と、自分が満足する目標が違う」・・・・主役は生徒なのに
「失敗したくない、成果を出さなければ、という思いが強くなる」
となってきます。
まずは、
「自分が主体性を伸ばすためには?」
を考え、
適切と思える誰かにサポートを求めて
自分の主体性を信じる経験をすることから始めてください。
人って結構、「恐怖から」行動しているんですよね。
~~~~~~~~~
※恐怖:
お金がなくなる。
留年する。
餓死する。
恥をかく。
怒られる。
居場所がなくなる。
信用がなくなる。
自分の人間性や能力のレベルがあからさまになってしまう。など
関連記事
-

-
社会生物本能の4タイプ
Flying Type / jennifermarquez[/caption] コミュニケ
-

-
相手がその気にならないと、何も変わらない。だから、自分の姿だけは見せておく。
コーチングをして意味がある人、ない人の話です。 もちろん、 「あの人は、こうしたらいいのに」と変
-

-
設問「どうやって仕事を覚えましたか?」
Facebookの新しいグループで下記の問いがありました。 設問「どうやって仕事を覚えましたか?」
-
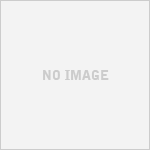
-
企業支援セミナー「報連相~指示待ち型から提案型~」(企業年金研究会)の参考サイト
以下は、2012年1月19日企業支援セミナー「報連相~指示待ち型から提案型~」(企業年金研究会)の
-

-
「すぐには教えない,でも詳しく教える」
リンク先は、高校数学の塾の先生の記事です。 タイトルだけでここの話は十分です。 「すぐには教
-
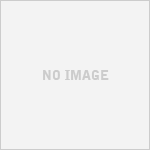
-
NORADサンタ2011
Merry Xmas! NORADのサンタ追跡プロジェクト http://www.noradsant
-
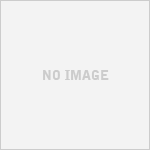
-
「メールの書き方を新入社員に教える」
「メールの書き方を新入社員に教える」 その指導のコツは、ほかの場面でも応用できそうです。
-

-
OTJでも、「できるようになったことをフィードバック」
先日、このような記事を書きました。 『Vol. 81 [仕事をしながら指導す
PREV :
やった回数か、やった時間か。
NEXT :
新年おめでとうございます